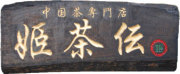店主一押し:伝統の四大名叢の座に着く白鶏冠は、別名「白衣君子」とも呼ばれ、他の岩茶より個性が強く、茶葉、茶底の鑑賞性も高い品種です。(四大名叢:大紅袍・鉄羅漢・水金亀) 今回ご紹介するものは、武夷銘岩にて、伝統手工で名高い名人(岩茶界の第一人者のお一人)が制作したものです。 この方は国家批物質文化遺産伝承人であり、またその茶農園は岩茶研究をしている領域でもあります。 この品種は、白化(*1)した茶樹が偶然発見されたことから生れました。岩茶の中でも色味が異なること、軽火で爽やかに仕上げられることも多く、岩茶の中では異質のタイプとして大変人気がございます。 中軽火の名人技で仕上げたこのお茶葉、まるで絵巻物の世界が広がるような香りと味わいです。 是非、丁寧に淹れていただき、産地の力強さを心身で感じていただけたらと思います。 (茶器は、小茶壷や小蓋碗など小さいもので丁寧に淹れてください) (*1) 白化:植物の葉のクロロフィル濃度が少なくなり、葉の色素や成分が変化(薄く)する現象。 (武夷山の茶樹:様々な条件が重なったことで白化した茶樹が偶然発見された) (白鶏冠は、健康的な成分としても知られています) 【岩茶の魅力とは?】 あくまで個人的な意見ですが・・・烏龍茶の中でも岩茶は特別な存在だと思います。他の烏龍茶に比べ香りは控えめでパッとしない印象があります。これは一般的な烏龍茶の尺度で岩茶を評価するからです。 他のお茶は主に鼻や舌でその素晴らしさを実感するものですが、岩茶は少し違います。岩茶は身体全体で感じるものだといえます。 さらに、茶葉にもよりますが、小さな茶壷で淹れますと一回分の茶葉で15煎近く飲めたりします(なかなか経済的)。多くの岩茶は最初の数煎も良いのですが、中盤から特に美味しくなっていくようです。この煎ごとの変化も魅力ですし、個人的には徐々に透明感が増して、トロリとなっていく感じが堪らないのです。 私は半日~丸一日使って、小さな茶杯でチビリチビリとお湯になるまで飲むのが好きです。茶杯にもほんの少しだけ入れコロリと舌の上で転がします。それは一滴、一滴貴重な黄金のしずくを体内に取り込んでいく感覚です。透明感がありますがエキスはとても濃厚です。煎を重ねるごとに、霧が立ち込める幽玄な世界に引き込まれ、時間の感覚も曖昧になっていくことでしょう。つまりリラックス度No.1のお茶でもあるのです。 【他人には言えないけど、こんなシンプルな飲み方も・・・】 タンブラーあまり格好の良い飲み方でありませんが、中国ではよく見かける美味しくてめちゃくちゃ簡単な方法をご紹介。 必要なものは耐熱性のコップと蓋になるものだけです。 1.まずコップに湯を注しあらかじめ温めておきます(湯は捨てます)。 2.そこにかなり少なめの茶葉を入れます。 3.これに茶葉が踊り出すほどの勢いで熱々の湯を注いで、上から小皿でも厚紙でも良いので蓋をして蒸らします。 4.茶葉が底に沈んで、湯が程よい色になれば飲み頃です(濃さはお好みで)。 この方法ですが、普通の淹れ方と比べて、甘味・エキス感がとても強く感じられるはずです(その代わり、香りはまあまあです)。また、しばらく置いておいても、意外と苦くなりません。お湯がなくなればまた注ぎ足してください。2-3杯は飲むことが出来ます。 ※ポイントは100度に近い熱湯と少なめの茶葉です。低い温度では茶葉が沈まず、口に入ってきて飲みづらいです。また、茶葉の量を少なめにするのは、長めの抽出時間で茶湯が濃くなり過ぎないようにするため。そして、数煎分の味を一度に愉しもうと言うわけです。(茶壷で淹れるときは一煎目と二煎目を茶海の中で混ぜ合わせたりしますよね)また、中国では多めに茶葉を入れますが、少なめの茶葉で長く抽出するほうがお勧めです。 以上、拍子抜けするほどシンプルな飲み方ですが、ぜひ一度お試しください。一味違う岩茶の魅力に巡り合えるはずです。 ※岩茶の産地である武夷山は1999年に世界遺産に登録され、国家重点自然保護区となっています。

商品カテゴリ
店舗営業時間 10:00-17:00 Tel 082-877-0078
- ■今日
- ■店舗休業日